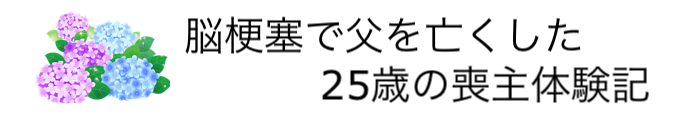本記事では喪主を経験したばかりの私から、
「精進落とし挨拶の必要性」と
「精進落としの挨拶例文」の
2点についてお話しさせていただきます。

喪主の体験記に関する詳細は、管理人Shinotoのプロフィールをこちらからご覧ください。
運営者紹介
この記事は、以下の3つの流れで説明していきます。
- 精進落としで挨拶をするタイミングと回数
- 各ポイント別の挨拶例文をご紹介
- 挨拶時の注意点
一般的に精進落としの流れは全国共通ですが、東北地方での私の実体験をもとにした記事となりますので、地域差がある場合は参考程度としてください。
挨拶のタイミングと回数
精進落としには、会の中で喪主から最低2度挨拶を行う必要があります。
ここでは精進落としの全体の項目と流れから、各挨拶のタイミングについてお話ししていきます。
ちょっとその前に….
「精進落とし」の意味を完全に理解できるている方って、そんなに多くないと思います。
そもそも精進落としって何?
「精進落としって何….」という今更聞けない方に対して、本来の役割と意味についてご説明させてください。
初めてお葬式を経験される方にとって「精進落とし」という文字面だけ見ると、一体なんのことだかわかりませんよね。
実は管理人である私も、自分自身が喪主になる以前にお葬式に参列した経験が一度もありませんでした。
そのため葬儀社の担当者と私の母親が「精進落としはどうしますか?」といった話をしている際、それが一体どのようなものか想像できなかった苦い経験があります。
それでは1文で説明します。
精進落としとは、
「主に家族の不幸などの神様を迎える祭事の期間には、仏教的に不浄と言われる肉や魚などを避けた食事を摂ることとなりますが、その期間に終了を告げる際に食べる料理」
といった意味になります。
もともと精進落としの儀というものは、仏教のしきたりに則ったものなのだったのです。
ちなみに日本で執り行われる葬儀の90%が仏教式のものですので、多くの方に当てはまることかと思います。
こちらの記事では、更に詳しい精進落としの意味や、当日の流れを説明しています。
精進落としとは?
精進落としの流れ
精進落としの具体的な流れは大きく分けて以下の5ステップです。
移動は葬儀社が用意するマイクロバスで全員で移動する場合や、各々が個人の車で移動するなどが一般的です。
基本的には、「本日はありがとうございました」といった内容となります。
挨拶が始まる前に参加者にお酌するなど、献杯の準備を忘れないようにしましょう。
お食事の間、喪主と遺族は、ご参加していただいた方にお酌をしながら軽く挨拶をし回ります。
中締めの挨拶では、これまでの感謝と今後のお付き合いをお願いする内容となるでしょう。この挨拶の直後から、帰られる方が増えていきます。
この中で喪主からの挨拶が必要となる箇所は、
「2. 喪主から開始の挨拶」と
「5. 中締めの挨拶」の
最低2回となります。
合わせて「6. 精進落としの終了」では、喪主から撤収・解散のお声掛けをする必要になる可能性が非常に高いです。
これから喪主を務める方は、ぜひ頭の片隅に置いといてください。
それでは各項目、どういった内容を伝えるべきかについて説明していきます。
喪主からの開始の挨拶
精進落としの会場に到着、全員が席に着いたら、喪主から開始の挨拶を行います。
この挨拶では、通夜から葬儀告別式、そして火葬まで葬儀の全体的な工程がとどこおりなく終えられたことに対するお礼などを伝えます。
合わせて出席者に対して参列や弔問への感謝を再度伝え、労う言葉をのせます。
中締めの挨拶
献杯で食事が開始してから1時間15分〜1時間半程度、タイミングを見計らって喪主から中締めのあいさつをします。
この挨拶では、改めての感謝もそうですが、今後のより一層のお付き合いをお願いする場と考えると良いです。
四十九日の法要や納骨日の予定日時が決まっていれば、この場で軽く伝えておくと良いでしょう。
撤収・解散のお声掛け
精進落としの席は、おおよそ2時間が一般的です。会場の時間的な都合により撤収・解散を促す声かけをします。
何度も同じこととなりますが、これまでの感謝と今後の良好なお付き合いをお願いする旨を一人一人丁重に伝えるようにしてください。
例文パターン
前置きが少し長くなってしまいましたが、挨拶例文のパターンをいくつか見ていきましょう。
本文の冒頭でもご説明しましたが、ここでは精進落としで発生する2度の挨拶とお声掛けの合計3パターンについて例文をご紹介していきます。
- 開始の挨拶
- 中締めの挨拶
- 解散、撤退のお願い
開始の挨拶
喪主の鈴木 太郎でございます。
遺族を代表いたしまして、お食事の前に一言ご挨拶申し上げます。
皆様、本日は誠にありがとうございました。
通夜から葬儀告別式、そして火葬まで葬儀全体が滞りなく終えることができたのは、ひとえに皆様方のお力添えがあったからでございます。
改めて感謝申し上げます。
ささやかではございますが、お食事をご用意させていただきましたので、お召し上がりください。
本日は誠にありがとうございました。
それでは早速、献杯の挨拶とさせていただきますが、今回は故人の兄にあたります『鈴木 実』さんより献杯の挨拶をしていただきます。
それでは『実』さん、お願いいたします。
合わせて皆様、献杯の準備のためにコップにお飲み物を注ぎください。
この場で挨拶をする人は喪主か遺族代表の方で、既に葬儀告別式で長めの挨拶をしているはずです。
そのため端的かつ要点のみをつかんだもの、具体的には出席者への感謝を伝える挨拶で問題ありません。
精進落としでの挨拶は、「挨拶」と「会自体の進行」のどちらの役割も果たしますので、次に控えている「献杯の挨拶」につながるようにしましょう。
またポイントとして、献杯の挨拶を行う人が滞りなく献杯できるよう、この時点でコップに飲み物を注いでいただくことを促してください。
中締めの挨拶
宴もたけなわではございますが、会場のお時間も近づいてまいりましたのでこの辺で中締めとさせていただきます。改めまして皆様、本日はお忙しい中、ご出席いただき本当にありがとうございました。
故人亡き今、我々遺族は一生懸命頑張りますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。
簡単ではございますが、これにてお礼の挨拶とさせていただきます。
それでは、お席の時間ですが、まだ30分程度ございますので、どうぞごゆっくりご準備ください。
お時間になりましたが、再度お声掛けさせていただきます。
仮に四十九日法事や納骨の日時が既に決まっている場合は、伝えておくのも良いでしょう。「四十九日法事ですが、4月5日の10時からを予定しております。後ほど別途きちんとした形でご連絡させていただきますのでよろしくお願いいたします。」
中締めの挨拶が終わり次第、徐々に帰られる人も出てくるので対応するよう考慮してください。
私の経験では、意外と中締めの挨拶が終わると帰宅される方が多く、故人の近しい親族以外はぞろぞろと帰宅されました。
終了・撤退のお声がけ
それではお時間となりましたので恐縮ではございますが、これにて閉宴とさせていただきます。
本日は誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
またお店の方にお願いして伝えてもらうでも大丈夫です。ちなみにですが私の場合、このお声がけはする必要がない程度、この時間にはうまく撤収できていました。
まとめ

それでは記事のまとめです。
精進落としの喪主からの挨拶は、大きく分けて2度あります。
- 「精進落としの開始時」
- 「精進落としの中締め」
- 「解散、撤退のお願い」
喪主は既に葬儀・告別式で大々的に挨拶を行なっているので、どちらの挨拶も端的なもので問題ありません。
注意点として、喪主は会の進行係りも務めるため、「挨拶」と「会の進行」のどちらの要素も含んだ内容となります。
会場時間の都合で、解散・撤退を促さなくてはならないこともあり、その時は丁寧にアナウンスしてください。
合わせて出席者が帰られる際には、返礼品をお渡しすることを忘れずに、出口までしっかりとお見送りすると良いでしょう。
これから精進落としを迎える方に。
精進落としとは?経験したばかりの筆者が流れと前段階の準備を徹底説明!
これから葬儀を迎える方に。
喪主を経験した25歳が、これからお葬式を迎える人にアドバイスを送る。